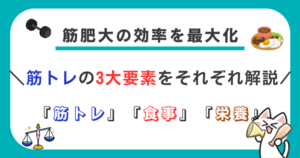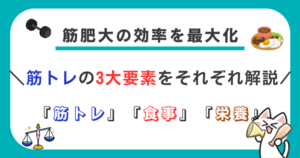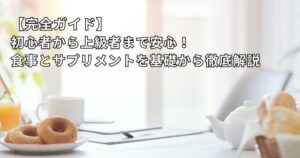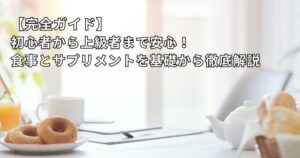【初心者向け】5大栄養素とは?体づくりに欠かせない栄養の基本をわかりやすく解説
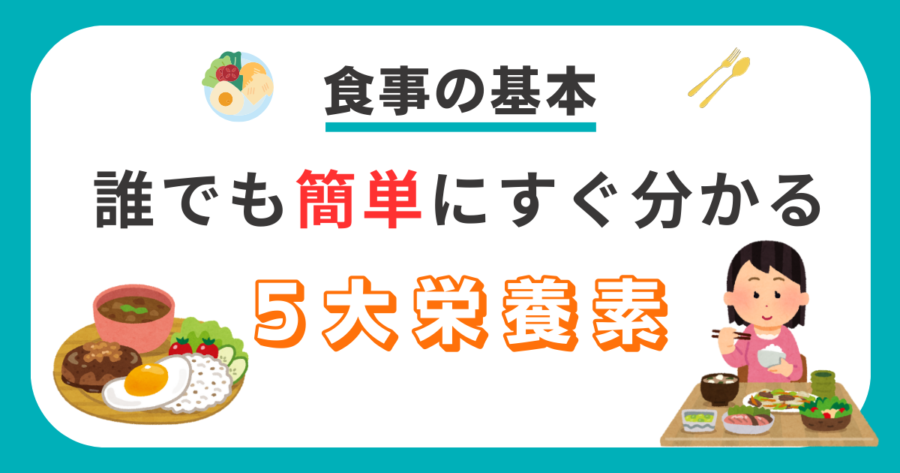
「食事って、なんとなく好きなものを選んでしまう…」
そんな日常、心当たりはありませんか?特に体づくりや健康を意識し始めたばかりの方にとって、何をどれだけ食べればいいのかは分かりにくく、不安になることもあるでしょう。
実際にパーソナルトレーニングの現場でも「運動を頑張っているのに結果が出ない」という声は多く、その原因の多くは 栄養バランスの偏り にあります。
本記事では、パーソナルトレーナー歴16年の経験から、体づくりに欠かせない「5大栄養素」の基本を初心者向けにわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、
- 5大栄養素の役割
- 食事での取り入れ方のポイント
- バランスを整えるコツ
が理解でき、日々の食事改善やトレーニング成果の向上につながります。
この記事を読めば、たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルの重要性と摂取のポイントが理解でき、日々の食事の質を高めることに役立ちます。
栄養バランスを整えて、トレーニングの成果を高めたい人はぜひ最後まで読んでください。
5大栄養素とは?【初心者が最初に知るべき基本】

人が健康を維持し、体を動かすために必要な栄養素は大きく5つに分けられます。これを 「5大栄養素」 と呼びます。
 たろうくん
たろうくんどれか1つが欠けても、健康や体作りには影響がでてしまうよ!
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 体を動かすエネルギー源 | ご飯、パン、いも類 |
| たんぱく質 | 筋肉・臓器・酵素など体の材料 | 肉、魚、大豆製品 |
| 脂質 | ホルモン生成・細胞膜・ビタミン吸収 | 魚、ナッツ、オリーブ油 |
| ビタミン | 代謝を助ける・健康維持 | 野菜、果物、きのこ |
| ミネラル | 骨や血液の材料、体の調整役 | 乳製品、海藻、ナッツ |
【炭水化物】体を動かすためのエネルギー源


炭水化物の基本(糖質+食物繊維)
炭水化物は「糖質」と「食物繊維」から成り立ちます。
- 糖質:即効性のエネルギー源
- 食物繊維:腸内環境を整え、血糖値の急上昇を抑える
糖質を摂りすぎると血糖値が乱高下しやすく、逆に不足すると集中力や持久力が落ちてしまいます。



食物繊維をしっかり取ることで、糖質の吸収もゆるやかになります。
炭水化物の種類と特徴
炭水化物には「単糖類」と「複合炭水化物」があります。
- 単糖類
- 吸収が早く、血糖値が急上昇
- 砂糖、白パン、菓子類に多い
- 運動直後の素早いエネルギー補給に有効
- 複合炭水化物
- ゆっくり吸収され、エネルギーが長く持続
- 米、パン、パスタ、など
- ダイエットやパフォーマンス向上に効果的
炭水化物の摂取のポイント
- 普段は米などの「複合炭水化物」を中心に
- 運動直後など、素早い回復が必要なときは単糖類も適量取り入れる
- 1回にまとめて大量に食べず、小分けで摂取すると血糖値が安定



たくさん食べると眠くなるよ、、、
【たんぱく質】筋肉だけじゃない!体の材料となる栄養素
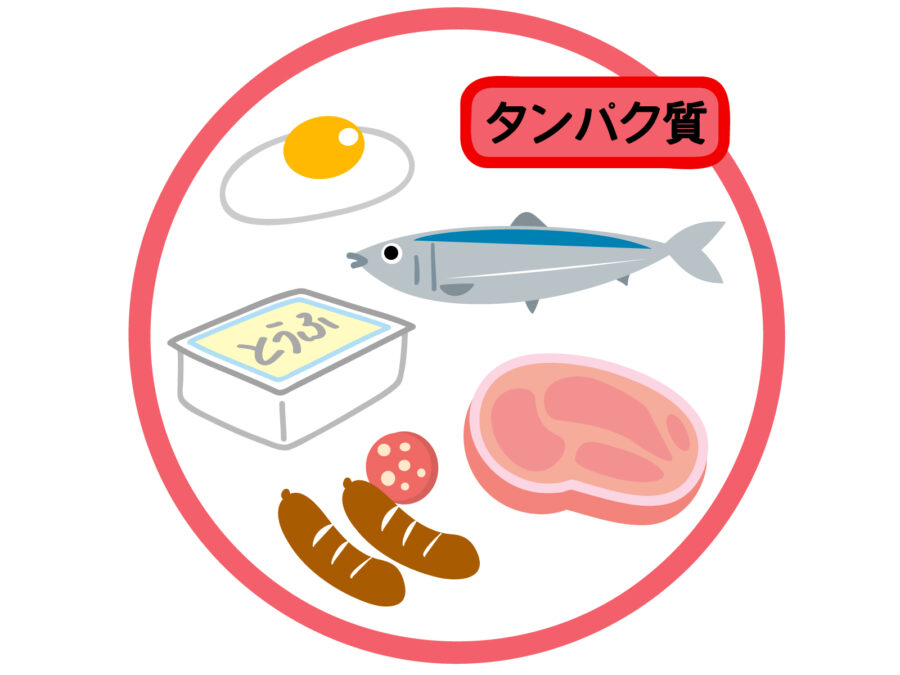
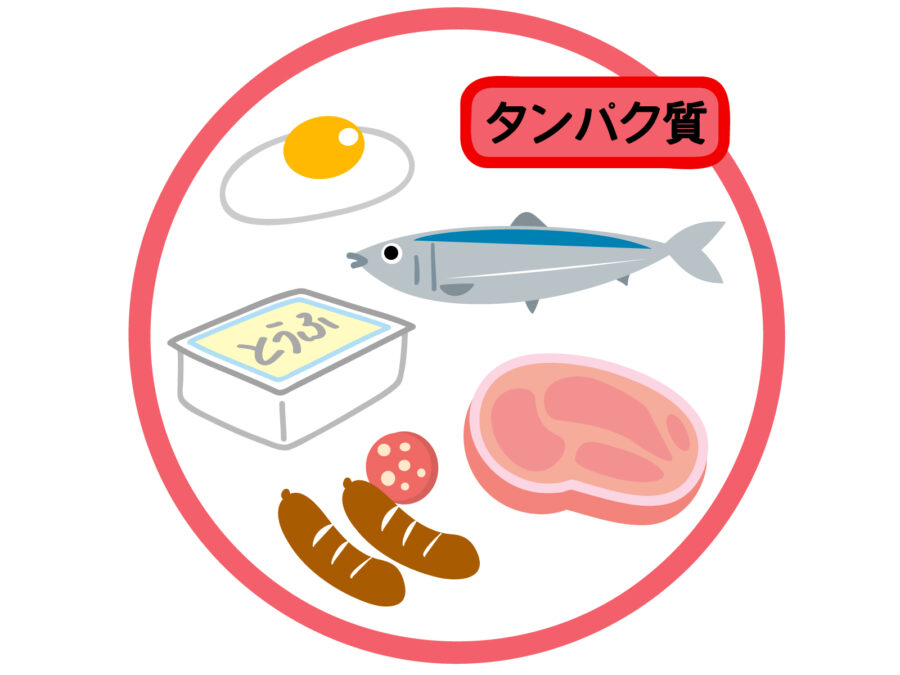
たんぱく質の役割
たんぱく質は筋肉の材料だけでなく、皮膚、臓器、血液、酵素、ホルモン、免疫細胞にも必要です。
たんぱく質が不足すると、体調を崩しやすくなる・代謝が落ちる・疲れやすくなるという悪循環になってしまいます。



筋トレをしている人はもちろん、誰にとっても欠かせない栄養素です。
動物性たんぱく質と植物性たんぱく質の違い
- 動物性:(肉・魚・卵・乳製品)
吸収効率が高く、筋肉合成に有利 - 植物性:(豆腐、納豆、枝豆など)
脂質が少なく、食物繊維やビタミンも同時に摂れる
タンパク質の摂取量の目安と食品例
一般の人の摂取量の最低限の目安は、体重1kgあたり1gとされています。
筋トレをしている人は筋タンパク合成のため、タンパク質の必要量が増加します。
体重当たり、1.5~2g/kg の摂取を目指すと筋肉の回復・成長に効果的です。
(例:体重60kg → 90g~120gのたんぱく質)
- 鶏むね肉、牛赤身、豚ヒレなどの肉類
- 魚(サバ、鮭、マグロなど)
- 卵、大豆製品(豆腐、納豆)
- ヨーグルト、チーズなどの乳製品



プロテインなら余分なカロリーを摂らずに、タンパク質を補給できるよ!
【脂質】実は必要!ホルモンやビタミン吸収に欠かせない


脂質の役割
- エネルギー源
- 細胞膜の材料
- 脂溶性ビタミンの吸収を助ける
脂質の種類と注意点
- 飽和脂肪酸
-
主に動物性。摂りすぎは動脈硬化リスク(例:ラード、バター)
- 不飽和脂肪酸
-
植物油や魚油(例:オリーブ油、青魚)
- トランス脂肪酸
-
加工食品に多く、摂取は極力控える(例:マーガリン、スナック菓子)
良質な脂質と摂取の目安
- 良質な油:えごま油、亜麻仁油
- 魚類:サバ、イワシ、サンマ(オメガ3脂肪酸が豊富)
- ナッツ類:くるみ、アーモンド(少量でも栄養価が高い)
- 総摂取カロリーの20〜30%が脂質が理想
- 摂りすぎ → 肥満・生活習慣病
- 不足 → 疲労、ホルモンバランス崩壊、肌の乾燥
▼重要なのは不飽和脂肪酸です。
・必須脂肪酸はオメガ3、オメガ6です。
・オメガ6は過剰摂取の傾向があります。
▼積極的に摂取すべきは、
・オメガ3(魚油、亜麻仁油)
・オメガ9(オリーブオイル)
脂質の種類にもご注意ください。



オメガいろいろあって覚えられないや、、、
【ビタミン・ミネラル】体の調整役として欠かせない


ビタミンの働きと種類
| ビタミン | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 視力・皮膚の健康 | レバー、にんじん、ほうれん草 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝、疲労回復 | 豚肉、玄米、卵 |
| ビタミンC | 抗酸化作用、免疫サポート | キウイ、いちご、ブロッコリー |
| ビタミンD | カルシウム吸収促進、骨の健康 | 鮭、きのこ、日光浴 |
| ビタミンE | 抗酸化作用、老化防止 | アーモンド、植物油 |
| ビタミンK | 血液凝固、骨形成 | 納豆、ブロッコリー |
※ 特にビタミンB群は相互に働くため、まとめて摂取するのがおすすめです。
ミネラルの役割と不足しやすい栄養素


ミネラルは骨や血液の材料になり、神経や筋肉の働きをサポートします。
| ミネラル | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| カルシウム | 骨・歯の材料、神経調整 | 牛乳、小魚、チーズ |
| 鉄 | 酸素の運搬、赤血球の材料 | レバー、赤身肉、ひじき |
| 亜鉛 | 免疫機能、代謝、味覚維持 | 牡蠣、牛肉、ナッツ |
| マグネシウム | 筋肉収縮、神経調整 | 玄米、豆腐、アーモンド |



カルシウム、カリウム、鉄、亜鉛は多くの年代で推奨量に達していません!
不足しやすいカルシウムについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
▶ カルシウム不足が招く4つのリスクと改善法|不足しがちな理由と摂取のコツ
5大栄養素をバランスよく摂るコツ
主食+主菜+副菜のバランスを意識する
食事の基本は 「主食(炭水化物)+主菜(たんぱく質)+副菜(野菜・海藻・きのこ)」 の組み合わせです。
この形を意識するだけで、自然と5大栄養素が揃いやすくなります。
- 主食(炭水化物) → ご飯、パン、麺、いも類
→ 体を動かすエネルギー源 - 主菜(たんぱく質) → 肉、魚、大豆製品、卵
→ 筋肉やホルモンの材料 - 副菜(ビタミン・ミネラル・食物繊維) → 野菜、海藻、きのこ、果物
→ 代謝を助け、体の調子を整える
不足しやすい栄養素を意識的に補う
現代人の食生活で不足しやすいのは「野菜・果物・海藻類」。
これらには ビタミン・ミネラル・食物繊維 が豊富に含まれています。
| 不足しやすい食品 | 含まれる主な栄養素 | 期待できる働き |
|---|---|---|
| 野菜 | ビタミンA・C・K、カリウム、食物繊維 | 免疫維持、血圧調整、腸内環境改善 |
| 果物 | ビタミンC、ポリフェノール、食物繊維 | 抗酸化作用、美肌、疲労回復 |
| 海藻・きのこ | ミネラル(カルシウム・鉄・ヨウ素)、食物繊維 | 骨の健康、貧血予防、代謝サポート |
👉 特に「彩りを増やす」と自然と栄養バランスも整います。
例:茶色い食卓(ご飯+焼き魚+味噌汁)に「緑(ほうれん草)」「赤(トマト)」「黒(ひじき)」を足すだけで栄養価がアップします。
不足しやすい栄養素をサプリメントで補う方法について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
▶ 【初心者向け】サプリメント完全ガイド|種類・効果・選び方までわかりやすく解説!
完璧を目指さなくていい理由
多くの人が「毎日きっちり栄養バランスを整えなければ」と考えて挫折します。
実際には 1食単位で完璧を目指す必要はなく、1日〜数日単位でトータルバランスが取れていれば十分 です。
- 朝食で野菜が少なかったら、昼や夜で多めに摂る
- 外食が続いたら、家での食事で整える
- スイーツを食べた日は、他の食事で糖質を控えめに
そして最も大事なのは 「なぜ食べるのか」を理解すること。
「体を動かすため」「疲れを取るため」「筋肉を維持するため」と目的を意識すると、自然と選ぶ食材も変わってきます。
まとめ
栄養の知識は一見むずかしく感じますが、ポイントはシンプルです。
「それぞれの栄養素の役割」を意識すること で、日々の食事の選び方がぐっと変わります。
最初から完璧を目指す必要はありません。
自分のペースで、目的を理解しながら食材を選ぶことで、体は少しずつ応えてくれます。
食事は健康やコンディションを整える大切な要素です。
無理なく続けられる方法を見つけて、理想のコンディションに近づいていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が日々の食事を考えるきっかけになれば嬉しいです。
関連記事