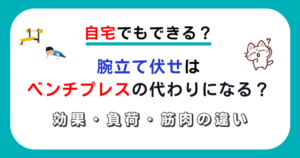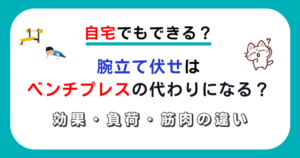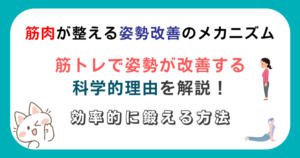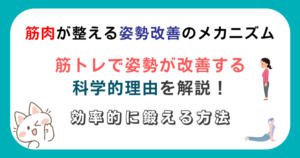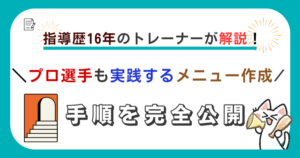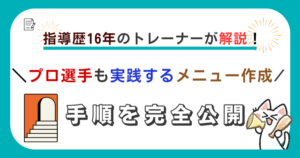使えない筋肉とは?筋トレしても動けない原因と改善法をプロトレーナーが解説
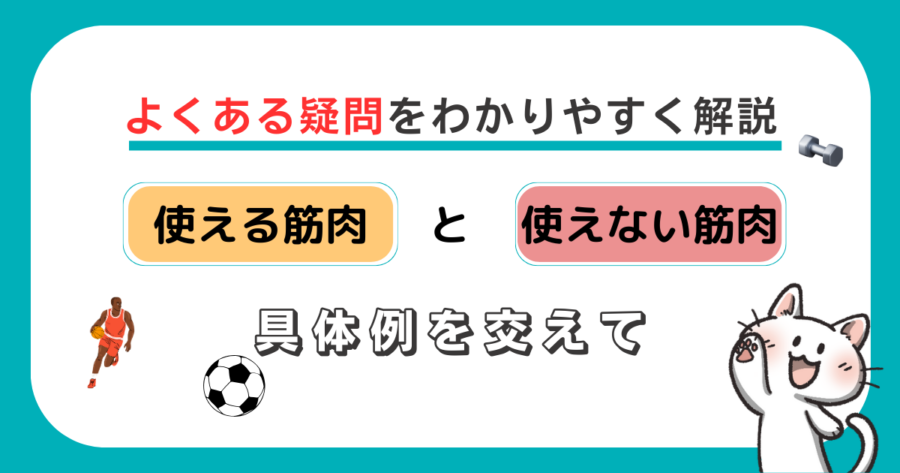
「筋肉はついてきたのに、動きがぎこちない」「力はあるはずなのにパフォーマンスが上がらない」
そんな経験はありませんか?筋トレに励む中で、「見た目は鍛えられているのに実際の動きに活かせない」という違和感を抱いたことがある方は少なくないはずです。
この違和感の正体こそが、“使える筋肉”と“使えない筋肉”の差です。本記事では、プロアスリートを指導してきた筆者が、見た目重視の筋トレと機能的な筋トレの違いを徹底解説します。
「筋肉をつけること」と「体を使えるようにすること」はまったく別物です。この記事を読むことで、目的に応じた鍛え方の選び方や、トレーニングの本質が理解できるようになります。
見た目だけでなく、実際に動ける“使える体”を手に入れたい人は、ぜひ最後まで読んでください。
 たろうくん
たろうくん使えない筋肉って言われるとショックだよね。
「使えない筋肉」の正体:筋肉をつける作業と、筋肉を使えるようにすることは別物


使えない筋肉とは
「使えない筋肉」という言葉は、筋肉がついているにも関わらず、競技能力が伴っていない状態を指します。一般的に筋力トレーニングをしていない人が筋肉隆々にも関わらず、動きが鈍い人に対して言うことが多いです。
筋肉をつける作業=筋トレ
筋トレとは筋肉を肥大させるための手段であり、筋線維に負荷をかけて損傷させ、回復過程で太く強くする行為です。これは筋肥大や筋力の向上を目的とする“物理的作業”であり、筋肉を使いこなす練習とは本質的に異なります。筋トレのみで「使える筋肉」を育てるのは難しく、補助的な役割として捉える必要があります。
多くのアスリートは、筋力を向上させるためにウェイトトレーニングを行っています。筋肉が肥大するのに伴って競技能力が向上するという認識がありますが、実際はそうとは限らないのです。
筋肉を使えるようにする作業=技術練習
筋肉を使えるようにするためには、技術練習が不可欠です。スポーツにおいては、筋力だけでなく、動作の精度やタイミング、柔軟性なども重要です。これらの要素が組み合わさって初めて、筋肉が効果的に使われるのです。
これは反復練習によって動きの精度を高める「スキル練習」であり、筋トレとは全く別のアプローチになります。筋肉に命令を出す「脳」と「神経」のトレーニングと言っても良いでしょう。
神経系の適応がないと、筋肉は使いこなせない
人間の動作は、脳→神経→筋肉という一連の流れでコントロールされています。筋トレで筋肉が増えても、この神経系の伝達が最適化されなければ、筋肉は効率よく動きません。使える筋肉を育てるには、神経と筋肉の連携を強化する“動作の質”にこだわることが重要です。
【具体例で考察】スポーツ選手が筋肉がついたのにパフォーマンスが落ちるメカニズム


野球選手:ウエイトで球速が落ちた例
高校野球などでありがちなのが、「ウエイトを始めたら球速が落ちた」というケース。ベンチプレスやスクワットで筋力は上がったが、フォームが崩れたり、関節の可動域が狭くなってしまったことが原因です。筋肥大が目的になりすぎると、投球に必要な連動性や柔軟性を失う可能性があります。



対策としては、筋トレと同時並行して、柔軟性を高める努力をすることが重要です。
サッカー選手:筋肥大で敏捷性が落ちたケース
下半身の筋力強化を意識しすぎた結果、体重が増えてしまい、スプリントや方向転換の速度が落ちてしまうこともあります。特にポジションによっては、筋力よりも軽さや敏捷性が求められることも多いため、筋トレのバランスが非常に重要です。
プロサッカー選手の筋トレがパフォーマンスに結びつかなかった詳細な例
海外リーグに挑戦したサッカーのプロ選手が、その年のオフシーズンから本格的に筋トレに取り組んだ例を取り上げます。
この例は、あるプロサッカー選手がオフシーズンに筋トレを重視しすぎた結果、筋肉量は増えたものの、動きが鈍くなり、試合でのパフォーマンスが低下したケースです。
スポーツ選手に限らず、筋トレ愛好家の方も同様の状況は起こり得ます。
高重量を扱うためにバルクアップしたとき、増えた体重を扱いきれずに日常生活の中で息切れしてしまうことなどがあります。



筋トレ愛好家の方はジョギングなどの筋トレ以外の運動にも取り組むこともオススメです。



体重も増やしすぎないで、たまにダイエットするといいよ!
格闘家:パワーアップしたがスタミナが持たない
パンチ力を高めるために筋トレで筋肉量を増やしたところ、動きが硬くなり、スタミナ切れが早くなったケースもあります。パワーとスピード、持久力のバランスを取ることが“使える筋肉”には必須です。



筋トレは目に見える成果がでるので楽しいです。
のめり込んでしまう人がいても不思議ではありません。



気がついたらボディメイクの方が気になって、、、
「使えない筋肉」にならないための対策


- 期分けして、計画性を持って取り組む
- スキル練習をおろそかにしない
- 体重増加に気をつける
- ストレッチを怠らない
筋肥大期・技術習得期・減量期などに期分けして、計画性をもって取り組む
トレーニングは期間を明確に分けて計画的に行います。
筋トレとスキル練習は、それぞれを明確に「期分け」して行うと、目的がぶれずにすみます。オフシーズンは筋肥大に、シーズンに近づくにつれて神経系や技術にフォーカスするといったサイクルが有効です。



技術練習とは競技やスポーツの練習のことを指します。
期分けせずに筋トレと技術練習を同時に行った場合
- 筋トレの強度が中途半端になる
- 疲労の管理が難しくなる
- 技術練習で怪我のリスクが高まる
- 技術練習時に筋肉痛で可動域制限が起きてしまう
これにより、筋肉をつけるだけでなく、実際の競技に必要なスキルも磨くことができます。
筋肥大期
- 高強度トレーニングに備えられる
- 疲労を管理しやすくなる
- 筋肥大用のトレーニングに集中できる
筋肥大期は疲労が溜まりやすいため、試合や競技のないオフシーズンや休養期に設定することで競技パフォーマンスに悪影響を与えずに土台を作れます。
技術練習期
- 競技の動作に特化したトレーニングができる
- 怪我のリスクを減らせる
- 筋出力を上げるトレーニングに専念できる
技術練習期は競技の動作に合わせたスキルの習得・向上に集中する期間です。
技術練習期に筋力&パワートレーニングを組み合わせることで、競技に必要な爆発的な力やスピードを高め、実戦でのパフォーマンスにつなげることができます。
減量期
計画性を持たずに短期間で減量に取り組むと、除脂肪とともに筋肉量も失ってしまいます。
- 筋肉量の減少にともない、筋出力が低下してパフォーマンスも低下してしまう。
- 筋肉の低下による体調不良や見た目の変化は、モチベーションを下げてしまう原因になることも。
- 筋肉量減少で代謝が落ちるため、減量後にリバウンドしやすい体質になる可能性がある。
筋肉量を保持しながら減量する方法について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
▶ 筋トレでつけた筋肉を落とさない減量術|本気で結果を出したい人の完全マニュアル
スキル練習をおろそかにしない
筋トレとスキル練習は別物と考える
筋トレは“筋肉の土台作り”であり、スキル練習は“動作の最適化”。それぞれを混同すると、「筋肉はあるのに動けない」状態になってしまいます。
「反復練習」こそが神経系の適応を生む
フォーム練習や基本動作の反復によって、神経系は動きを記憶します。回数と頻度を重ねることで、筋肉が“自然に使える”ようになるのです。
スポーツの世界では、レベルがあがるほど、他の選手との差は競技スキルの差になってきます。
筋トレは短時間で力を出し切るほうが効率が高いですが、スキル練習はそうはいきません。技術の習得、それを反復して体に覚え込ませるためにも多くの時間がかかるものなのです。



そもそも簡単に習得できるスキルなら、他の人にも簡単にできてしまい差がつきません!
体重増加に気をつける
筋肉量が増えると体重も増加しますが、体重が増えすぎると動きが鈍くなる可能性があります。適切な体重管理が求められます。
筋肥大=正義とは限らない
筋肉量が増えると見た目は頼もしくなりますが、スポーツにおいては“体重あたりの出力”がパフォーマンスに直結します。無計画な筋肥大はかえってマイナスに働く場合もあります。
競技特性に合った体重管理を意識する
競技によって理想体型は異なります。マラソン選手とラグビー選手では、必要な筋量も体重も違います。自分の競技や目的に合わせた体重設計が重要です。
ストレッチを怠らない
関節可動域の確保は「使える筋肉」の土台
筋トレで筋肉が硬くなると、関節の可動域が狭まり、動作効率が落ちます。可動域が確保されてこそ、筋力は最大限に活きるのです。
筋肉が硬いと、力の発揮効率も落ちる
筋トレは筋肉が収縮するときに力を発揮します。疲労してくるとコリが残って筋肉が解れにくくなってしまいます。
ストレッチを意識的に行うことで、柔軟性を保つことができて筋肉の持っている本来のパフォーマンスを維持できるのです。



筋トレ、スキル練習、ストレッチの3点セットは大事だよ!
パフォーマンスを引き出すストレッチについては、こちらの記事をご覧ください。
▶ 動的ストレッチのやり方と注意点|パフォーマンスを引き出す効果的な準備法
まとめ
「使えない筋肉」とは、筋肉がついているにも関わらず、運動能力が伴わない状態を指します。
そうならないためには、筋トレだけでなく、技術練習や体重管理、ストレッチなど、総合的なアプローチが必要です。
プロスポーツ選手が真のパフォーマンスを発揮するためには、筋肉をつけることと同時に、それを使えるようにするための努力が不可欠です。
- 筋肥大期・技術習得期・減量期などのに期分けして、計画性を持って取り組む。
- スキル練習(神経系のトレーニング:反復練習)を疎かにしない。
- 競技特性にあった体重管理をする。
- 柔軟性を保つためにストレッチを怠らない。
以上のものを確認して、見た目に見合った筋肉と言われるように頑張りましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。
「使えない筋肉」についての疑問が解消できていましたら嬉しいです。
関連記事