トレーニング完全ガイド|始め方・組み方・続け方を現役トレーナーが解説
「筋トレを始めたいけど、何から手をつければいいのかわからない」
「自己流でやってるけど、これで合ってるの?」
そんな不安や疑問を抱えている方は少なくありません。トレーニングは始め方だけでなく、目的に合った組み方や、継続する工夫まで考えることで、効果が大きく変わってきます。
本記事では、パーソナルトレーナー歴16年、初心者からアスリートまでをサポートしてきた筆者が、「始める・組む・続ける」の3つの軸から、レベル別に筋トレの進め方を完全ガイドします。
これを読めば、自分に合ったトレーニングの始め方がわかり、途中で挫折しにくく、目標に応じて進化するための考え方が身につきます。
正しい知識を身につけて、無駄なく、最短ルートで成果を出したい人はぜひ最後まで読んでください。
【トレーニングの基本】トレーニングの主な種類と目的の違い

筋トレと有酸素運動の違いや、目的別の使い分けをより深く理解したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶ 筋力トレーニングと有酸素運動の違いを徹底解説!最適な運動選びのポイント
【トレーニングの要素】筋力・持久力・パワーの違いを表でわかりやすく解説
| 特性 | 筋力 | 筋持久力 | パワー |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 最大出力を上げる | 長く動き続ける | 一瞬で爆発的に動く |
| 負荷の大きさ | 高重量(80〜100% 1RM) | 低〜中重量(40〜60% 1RM) | 中〜高重量(30〜70% 1RM) |
| 回数の目安 | 1〜5回 | 12〜20回以上 | 3〜6回(できるだけ速く動作) |
| 主な筋繊維 | 速筋 | 遅筋 | 速筋+神経系 |
| トレーニングの対象 | 筋力競技、基礎力UP | 体力向上、引き締め、機能性UP | スポーツ選手、動作スピード強化 |
- 筋力
-
・何かを一瞬だけ、全力で押したり引いたりする力のこと。
・速筋(スピードと力に優れる筋肉)を主に使います。
・鍛えると重いものが持てるようになり、他のトレーニングの基礎になります。 - 持久力
-
・軽めの動きを、ずっと繰り返し続けられる力のこと。
・遅筋(スタミナに優れる筋肉)を主に使います。
・疲れにくくなり、日常生活が楽に行えるようになります。 - パワー
-
・力 ✕ スピードで決まる力。筋力だけでなく、スピード要素が加わる。
・速筋+神経系(脳と筋肉の連携が重要)の両立が要です。
・「速く・強く」動くための能力。アスリートや競技者に不可欠です。
 JUN
JUNこれらの目的に応じて、
種目選びやセット数・回数が変わります。
筋肥大とは、筋肉のサイズ(見た目)を大きくすることを指します。
筋力や筋持久力が「何がどれだけできるか(=機能向上)」なのに対し、筋肥大は「見た目の変化=筋肉が盛り上がること」を目的とします。
筋肥大は、トレーニングの強度・回数・目的でいうと…
- 筋力トレーニング(1〜5回の高重量)
- 筋持久力トレーニング(15回以上の低重量)
ちょうど中間にあたる、『中重量×中回数(8〜12回)』での刺激が最も効果的です。
「見た目を変える筋トレ」と「機能を高める筋トレ」の違い
◆ 見た目改善(ボディメイク・筋肥大)
- 目的:筋肉量を増やし、体を引き締める
- 代表的手法:中重量×中回数(8〜12回×3セット)
- 具体例:ダンベルプレス10回×3、ラットプルダウン12回×3
- 特徴:筋肉に“パンプ”を感じるような刺激を意識し、セット間インターバルは60〜90秒程度
◆ 競技パフォーマンス向上(スポーツ機能)
- 目的:ジャンプ力、ダッシュ、投げる力などの向上
- 代表的手法:軽重量×高速動作(スピード) or 高重量×低回数(神経系刺激)
- 具体例:ジャンプスクワット、クリーン、スプリントインターバル
- 特徴:動作スピードとフォーム重視。セット間インターバルは2〜3分とやや長め。
◆ なぜ目的の明確化が重要なのか?
目的が明確でないままトレーニングを続けても、「なんとなくやってる」状態から抜け出せません。たとえば、筋肉を増やしたいのに軽い負荷で延々と回数をこなしても非効率です。
【初心者向け用語集】筋トレでよく使われる言葉の意味4選
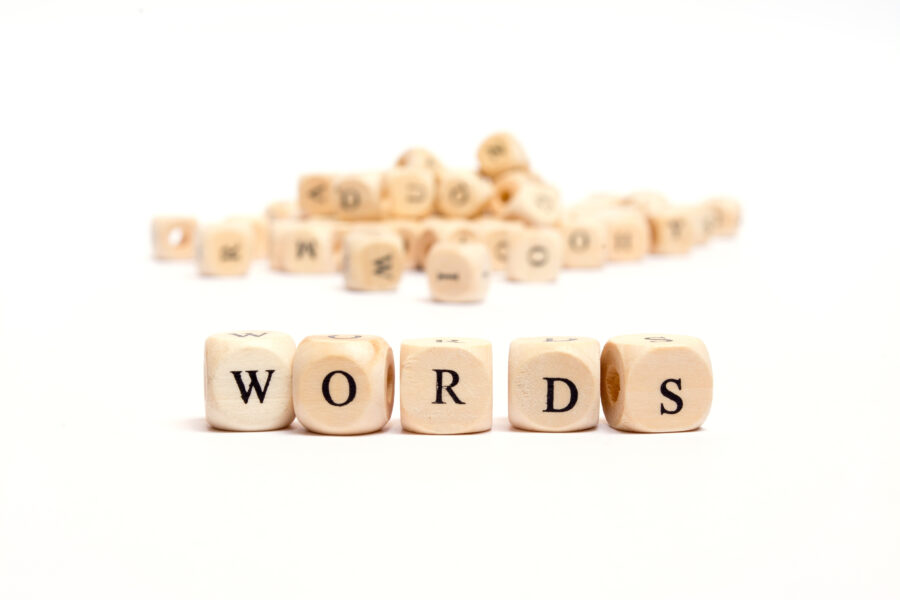
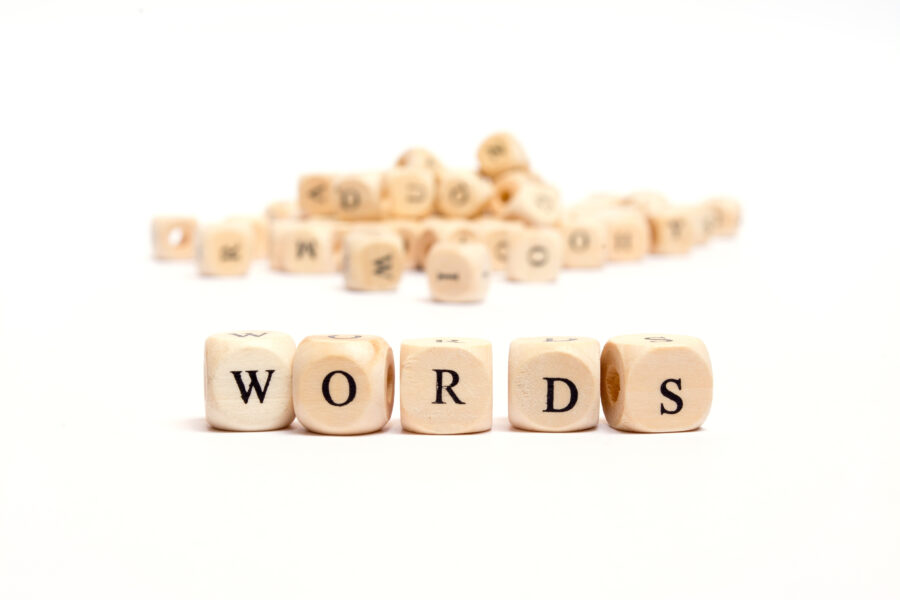
セット・レップ・RM・インターバルとは?筋トレ用語をわかりやすく解説
| 用語 | 意味 | 例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| レップ(Rep) | 1回の反復動作。 | スクワット10回 | 動作の質と回数を両立する |
| セット(Set) | レップのまとまり。 | 10回×3セット | 1セットごとに短い休憩がある |
| RM(Repetition Maximum) | 最大反復可能回数(限界重量の目安) | 10RM=10回が限界の重量 | 負荷設定の基準になる |
| インターバル | セット間の休憩時間。 | 筋肥大なら60〜90秒が目安 | 目的に応じて調整可能 |



ぼくはこの4つで十分だよ!
より細かい筋トレ用語を知りたい方はこちらをご覧ください。以下の記事では図解を使って15語をわかりやすく紹介しています。
▶ 【初心者必見】これさえ押さえれば大丈夫!筋トレ用語15選をわかりやすく解説
【初心者向け】筋トレの負荷設定の基本と進め方
トレーニング初心者のための負荷設定の基本
初心者はRM(限界まで持ち上げられる重さ、回数)にこだわらなくて問題ありません。最初は、「あと2〜3回はできるな」というところでやめてしまっても十分です。



初心者は毎セット、余裕がある状態でやめても大丈夫。
上級者になると、RMやRPE(主観的強度)などを活用して、計画的に負荷を調整していくと良いです。
▼RMやRPE(主観的強度)についての詳しい説明はこの記事の中盤で解説しています。
初心者が限界までやらないほうがいい理由とは?
- 限界まで追い込むと、フォームが崩れたり、ケガのリスクが高くなります。
- 特に初心者は筋肉より神経系の疲労が先に来るため、フォームの習得を優先させてください。
「プログレッシブ・オーバーロード」とは?意味と活用法を解説
プログレッシブ・オーバーロードとは、「徐々に負荷を増やしていく」という筋力トレーニングの基本原則です。
筋肉や体力を成長させるためには、トレーニングの重量や回数、セット数、難易度などを少しずつ高めていく必要があります。
- 徐々に重量を上げる(例:10kg→12.5kg→15kg…)
- 反復回数を増やす(例:10回×3セット→12回×3セット)
- その種目のセット数を増やす(例:3セット→4セット)



毎週少しずつ負荷や強度を上げていく意識を持つことが、長期的な成長を実現する秘訣です。
継続のカギは「ちょうどいい負荷」の見つけ方
毎回限界まで頑張る必要はありません。続けることのほうが大切です。
目安は、「あと2回はできそう」というところでセットを終えることです。
ベンチプレスやスクワットで潰れるまで頑張るというのは、効率がよくありません。
上級者ほどフォームが乱れる前にセットを完了させています。



頑張り過ぎも良くないんだね。
トレーニングの強度や負荷設定について、次のような関連記事があります。ぜひ参考にしていただけると幸いです。
▶ 【Q&A】筋トレで10回3セットが好まれるのはなぜ?
【レベル別ガイド】初心者・中級者・上級者の筋トレメニューの考え方


男性と女性でボディメイクの考え方に違いはあるのか?気になる方はこちらの記事もあわせてどうぞ。
▶ 【Q&A】男性と女性で、ボディメイクのアプローチに違いはあるの?
初心者が最初にやるべき筋トレ3ステップ
初心者の最大の目的は「継続と習慣化、そして正しいフォームの習得」です。筋肉を大きくすることや記録を更新することよりも、まずは「続けること」が何より大切です。
① 週何回・何をやるかの目安
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 頻度 | 週2〜3回(無理なく継続できる回数) |
| 時間 | 1回30〜45分程度 |
| 種目数 | 5〜6種目が基本(全身をまんべんなく) |
- 全身トレーニングがおすすめ
→ 1部位に偏らず、全体をバランスよく鍛えることで姿勢改善や基礎代謝の向上にもつながります。 - 初心者向け種目例
- スクワット(脚・体幹)
- 腕立て伏せ(胸・肩・腕)
- プランク(体幹)
- 懸垂 or ロウ系(背中)
- クランチ(腹筋)
📌 ポイント:まずは「軽く感じるくらいの重量」でOKです。フォームが安定してきたら、少しずつ負荷を上げましょう。



初心者のうちは、種目数を絞って取り組む方が上手くいきます。



全身トレーニング法なら週1回しかできなくても、
すべての部位を週1回は刺激できるよ!
② とにかく正しいフォーム重視で
- 正しいフォームはケガ防止と効果的な刺激の両方に直結。
- 間違ったフォームのまま続けると、逆に姿勢が悪くなるリスクも。
フォーム確認の方法:
- スマホで動画撮影 → 後で自分の動きを客観視する。
- 鏡を使ってリアルタイムにチェックする。
- 初心者ほど、「軽い負荷で完璧な動き」を徹底する。



毎回ウォーミングアップでフォームを固める意識でやるといいよ!
- スクワットで膝が内側に入る(ニーイン)
- プッシュアップで腰が反る or 顔だけ下がってしまう。
- プランクで肩がすくんでしまう。



こうした癖は早めに矯正しないと、
上達が遅れる要因になります。
自重トレの負荷を最大限に高める方法を解説しています。ぜひご覧ください。
▶ 【器具なしでも筋肥大】自重トレーニングの負荷を最大化する方法を徹底解説
筋トレ中級者の伸び悩みを打破する方法
中級者になると、「正しいフォームでやっているのに、伸びない…」という壁にぶつかりがちです。ここで必要なのが「バリエーションをつける」と「記録を振り返る」という方法です。
① 変化をつける「可変性(バリエーション)」の考え方
「同じ種目・同じ回数・同じ重さ」では、体は成長しません。筋肉は“慣れ”によって反応が鈍くなるため、定期的な変化が必要です。
- 重量(例:10kg → 12kg)
- 回数/セット数(例:10回×3 → 12回×4)
- 種目の順番(いつも後半にやってる背中を1種目目に)
- 動作スピード(ネガティブ動作をゆっくり)
- 器具の種類変更
- マシン → フリーウェイトへ
- バーベル → ダンベル
- スミスマシン → ケーブル種目
📌 重要なのは「狙いがブレない範囲で変える」こと。変えすぎても一貫性がなくなり、効果が見えにくくなります。
② データを取って改善する習慣
「記録なしに成長なし」と言っても過言ではありません。
中級者以降は、感覚より数値と記録に向き合っていく必要があります。



より工夫して頑張っている人が、平均よりも上に行けるのです!
- 重量・回数・セット数:(例:ベンチプレス60kg×8×3)
- RPE(主観的なきつさ):例:7=「あと3回できそう」
- 体重・体脂肪率:(週1回程度)
- 停滞・成長している部位の自覚
記録方法例:
- スマホのメモ帳
- 筋トレ専用アプリ(例:筋肉手帳、Strong、Fitnotes、MyFitnessPal)
- トレーニング動画を記録してフォーム確認+経過観察
📌 数値の変化がモチベーションにもなるので、「可視化」する習慣は中級者の伸びを大きく左右します。
筋トレ上級者向けの効果的なトレーニングテクニック
上級者は、ただ「重いものを持つ」だけでは成長が頭打ちになります。ここからは、強度をコントロールする力と内面の感覚がより重要になってきます。
① 限界まで追い込まないための上級者のコントロール
- 毎回100%で挑むと、神経系が疲れすぎて逆効果です。
- 適度な強度(最高重量の70〜85%)を自在に操る能力が鍵となります。
- 「今日は感覚的に75%で攻める」といった調整ができると、高頻度でもオーバーワークを防げます。
💡 週5回以上の高頻度トレーニングをこなす人ほど、「抜く日」「追い込む日」を分けています。
② 刺激の質を高める「内的意識(マッスルマインドコネクション)」
ただ動かすだけでなく、「筋肉の動きを感じる」ことが成果を左右します。
マッスルマインドコネクションを高める方法:
- 動作をゆっくりする(特にネガティブ局面)
- 鏡を見て確認するより、筋肉の収縮感に集中する。
- 手でターゲット筋を触れて意識を高める。



ネガティブ局面とは、重りを下ろしているタイミングのことだよ。
📌 上級者ほど、「心と筋肉の対話」を重視しているといいます。フォームが完成した後に“質”を高めるための意識の持ち方と言えます。
RMやRPE(主観的強度)などを活用する
上級者は、RM(Repetition Maximum)やRPE(主観的運動強度)を活用して、計画的に負荷を調整します。
- RMは「限界で何回反復できるか」の重さを表す指標で、筋力なら1〜5RM、筋肥大なら6〜12RMなど、目的に応じた設計に役立ちます。
※1RMは1回しかできない重量。5RMは5回しか反復できない重量です。 - RPEは「あと何回できそうか」という主観的な強度です。10が基本となり、RPE8(あと2回できる)、RPE9(あと1回)などで管理します
この2つを組み合わせることで、
- 記録の伸びが鈍くなってきた時期でも、安全かつ効率的に追い込むことができ、
- その日の体調や疲労度に合わせて柔軟に強度を微調整することが可能になります。
代表的な筋トレ種目の違いを詳しく知りたい方には、スクワットとデッドリフトの違いを解説した記事もおすすめです。
▶ スクワットとデッドリフトの違いとは?|動作の違いと目的別の使い分けを解説
筋トレ効果を最大化するフォームとコントロールのコツ


ゆっくり動かす・スロートレーニングの効果とメリット
TUT(Time Under Tension)が長くなるから
動作をゆっくり行うことで、筋肉が緊張している時間(TUT)が伸びます。この「じっくり効かせる」刺激は、筋肥大を促進するうえで非常に有効です。
反動をなくして狙った筋肉に効かせられる
反動(チーティング)を使わないことで、筋肉単体の力で動作を完遂できます。これにより、効かせたい部位をピンポイントで刺激できます。
ケガのリスクを下げられる
スピードを落とすことで動作の安定性が高まり、関節や腱への不要なストレスを減らせます。初心者にも安全なアプローチです。
鏡での見た目よりも体感を重視する理由とそのメリット
外見に頼るとフォームが適切でないことも
鏡で姿勢を確認するのは大切ですが、それに頼りすぎると「見た目のトレーニングフォームだけカッコよくて、筋肉は正しく使えていない」状態になりがちです。
広背筋を鍛えるときは背中を反ったほうがいいですが、僧帽筋を鍛えるときは背中を丸めて僧帽筋にストレッチをかけた方が効かせることができます。



カッコいいフォームが目的に合ったフォームとは限らないんだね!
内的意識(自分自身の感覚)を高めてトレーニングの質を上げる
- 手応え(重さを感じる)
- 張り(ターゲット筋の膨張感)
- 疲労感(狙った部位が正しく疲れる)
これらの内的指標を信じてトレーニングを続けることで、感覚と動作の一致度が増し、筋肥大やパフォーマンス向上に直結します。
ベンチプレスでバーが胸につかないのはという方は、フォームの見直しが特に重要です。よくある原因とその対策を以下の記事で解説しています。
▶ 【Q&A】ベンチプレスでバーが胸につかないのはなぜ?
初心者でもできるトレーニングメニューの作り方と見直し方
筋トレメニューは種目より“全体設計”が重要な理由
初心者〜中級者がやりがちなのが、「YouTubeで見たメニューをとりあえずやってみる」というパターン。しかし、効果的なプログラムは“種目の意味と順番”に根拠があるべきなのです。
人気YouTuberのトレーニングをそのまま真似することの落とし穴について、Q&A形式で詳しく解説しています。
▶ 【Q&A】憧れのYouTuberのトレーニングをそのまま真似してはいけないのはなぜ?
押す/引く/体幹のバランスを取る
- 押す動作(ベンチプレスなど)
- 引く動作(懸垂やロウイング系)
- 体幹(プランク、デッドバグなど)
全身の筋肉のバランスを整えることで、姿勢改善やケガ予防にもつながります。
自重トレーニングの代表種目「腕立て伏せの負荷ってどのくらい?」と気になる方は、こちらの記事でベンチプレス換算も含めて解説しています。
▶ 【Q&A】腕立て伏せの負荷ってどのくらい?ベンチプレスに換算できるの?
疲労・可動域・技術に応じて種目を配置
- 疲れやすい部位(脚・背中)は前半に
- 可動域の広い動作や複関節種目は最初に
- 単関節種目や軽負荷種目は補助・仕上げとして配置



大きな筋肉を先に、小さな筋肉を後半に持っていくといいです。
メイン・補助・仕上げの役割を明確に
- メイン種目: 高重量/複関節(例:スクワット、デッドリフト)
- 補助種目: 中重量/フォーム重視(例:ダンベルプレス)
- 仕上げ種目: 軽重量/高回数(例:ケーブルクロス)
筋トレメニューを変えるタイミングとその判断基準
失敗しない「プログラム変更」のタイミング
- 2〜3週間記録が伸びていない。
- フォームが雑になってきた。
- モチベーションが下がってトレーニングが楽しくない。
変更方法の例:
- 同じ部位でも別の刺激を加える(ベンチプレス → ダンベルフライ)
- セット法を工夫(スーパーセット・トライセットなど)
- 分割法を変える(全身法 → 上半身・下半身分割)
📌 変更は「頻繁すぎず、でも停滞しないうちに」が理想。



小さな変更で新しい刺激を加えるのがポイントだよ!



3〜6週ごとの軽い調整が最も効果的です。
具体的な筋トレメニューの作成手順については、以下の記事で7ステップで詳しく解説しています。
▶ 【初心者OK】指導歴16年のプロが解説!プロ選手も結果を出した筋トレメニュー作成手順を公開
筋トレ記録のつけ方|成長を実感するための習慣術


筋トレを記録すると効果が見える理由とは?
トレーニングの進捗を数字で確認することで、成長を実感でき、モチベーションもアップします。
「なんとなくやってる」状態から脱却できるのが大きなメリットです。
筋トレ記録のつけ方とおすすめアプリ・ノート
紙・ノート派
- 日付/種目/重量/回数/感想を記録
- 思考整理や自己対話に役立つ
アプリ派
- 筋トレMEMO、Strong、FitNotes、MyFitnessPalなどが人気
- 自動グラフ化・過去比較・RPE記録が可能



アプリ派の人は筋トレMEMOが
無料で使えておすすめです!
動画記録派
- フォームチェックや自分のクセ確認に最適
- 毎週1〜2種目を撮って保存がおすすめ
筋トレは「昨日の自分」に勝つ記録型競技
- 1週間前より1回多くできた。
- 先月より重い重量が扱えた。
- 体脂肪率が減って、筋肉量が増えた。
この「小さな成功体験の積み重ね」が継続の原動力になります。
成長を“可視化”することは、筋肉以上に「自信」を育ててくれます。
筋トレを習慣化するためのコツ|継続できる人の工夫とは?
筋トレは“やる気”より“仕組み”で継続できる
トレーニングを続けるには、「やる気」に左右されるのではなく、「仕組み化」で対策するのが効果的です。トレーニング環境をすこし工夫するだけで、運動のハードルが一気に下がります。
ジム派の人は前日の夜にウェアを用意しておく
着替えの手間を減らすことで、朝や帰宅後すぐにトレーニングへ移行しやすくなります。
目に入る場所にウェアを置いておくと、「やらなきゃ」という意識が自然に生まれます。



ジムに行ってる人はバックに入れておくといいよ
自宅トレーニングの人はトレーニング器具をすぐ使えるように部屋を整頓する
自宅トレーニングなら、ダンベルやヨガマットをリビングに広げられるスペースを常に確保するのも効果的です。



一旦片付けてから始めるのは大変だよ〜。
モチベーション維持や継続の工夫として、効果的なトレーニングギアを使うのも一つの方法です。おすすめギアを紹介した以下の記事もぜひご覧ください。
▶ 筋トレ効果を最大化!初心者から上級者までおすすめのトレーニングギア6選
トレーニングを日常に溶け込ませる
「週3回筋トレ」ではなく、「月・水・金は筋トレの日」と決めて、生活サイクルに組み込むのがポイント。
時間帯も固定すれば、脳と体が「やるのが当たり前」と覚えます。



ほとんどの人が曜日でトレーニング部位を決めています。
筋トレを継続できる“できた日だけ記録”のススメ


筋トレ継続の第一歩は「カレンダーに〇」から
トレーニングした日だけ〇をつける簡単な記録法でも、効果は絶大です。
壁や手帳に貼ったカレンダーに〇が並ぶと、「続けている自分」が可視化され、自信がつきます。
ポイントは“完璧を求めない”こと。抜けがあっても大丈夫です!
続けること自体が最大のやる気になる理由
習慣化の目的は「結果を出すこと」ではなく「続けること」。
記録をつけることで、自分の行動パターンやサボりがちなタイミングも客観視できるようになります。



トレーニングをサボってしまっても全く問題ありません。
どんなときに休みたくなるか、傾向をつかむだけでも有益です!
筋トレのやる気が出ないときに試したい回復テクニック
筋トレの目標設定を“今日できること”に分解する方法
例:半年でベンチプレス100kgが目標 → 今日のトレーニングで1セット多く頑張る
目標が大きすぎると、途中で挫折しがちです。
そんな時は、「次の1セット」「あと1回」など、小さなゴールに再設定することが有効です。
- ベンチ100kgを目指す → 今週は90kgを3回成功させる
- 体脂肪を5%落とす → 今週は間食を1回減らす
モチベーションを上げるには「小さな成功体験」から
「できた!」という達成感は、やる気をあげるスイッチになります。
短期的な目標を達成すれば、「自分にもできる」という自己肯定感が高まります。
SNSやYouTubeを活用した筋トレモチベーション維持法
筋トレ系YouTubeでやる気を保つ方法
お気に入りのトレーナーやフィットネスYouTuberの動画を見ることで、やる気が自然と湧いてきます。
特にルーティン動画やモチベーション動画は効果的です。



トレーニング動画を見るだけでもやる気が出るね!
筋トレ仲間をSNSで見つけて継続力アップ
X(旧Twitter)やInstagramで、「#筋トレ記録」「#宅トレ仲間」などのハッシュタグを使って共通の仲間と交流すると、継続の意欲が高まります。
SNSでは「見る側」も「見られる側」も刺激を受けることができます。
- 進捗を投稿して見られることで「見られている意識」が働く
- 他の人の成果が刺激になり、自分も頑張ろうと思える



週1回のSNSでの投稿でも、やらなきゃってなるよ!
よくある質問(Q&A)|トレーニングの疑問を一気に解決!


トレーニングに関する小さな疑問や不安は、放っておくとモチベーションの低下につながります。
気になることは早めに解消して、「納得しながら続けられる」環境を整えましょう。
まとめ
トレーニングは、筋肉を鍛えるだけでなく、「体を理解し、目的に合わせた正しい努力を積み重ねる」ことが成功のカギです。筋力・持久力・パワーといった基本的な概念を押さえ、目的に応じた種目や回数を選ぶことで、最短ルートで成果に近づくことができます。
初心者であればまずは全身をまんべんなく鍛え、フォームを徹底的に意識することが重要です。中級者以上になったら、変化をつけたり記録を残す習慣を取り入れることで停滞を防げます。そして上級者にとっては、単に重さや回数を追うのではなく、内的感覚や神経系のコントロールといった質の高いアプローチが求められます。
また、どのレベルでも共通して大切なのは「継続する仕組みづくり」です。やる気に頼るのではなく、環境・習慣・外部の刺激をうまく取り入れて、日常の中にトレーニングを溶け込ませましょう。
本記事で紹介したような知識やテクニックを、まずは自分に合った形で1つずつ取り入れてみてください。「正しく続けること」が、最も効率のよいトレーニング法であることを、ぜひ体感していただければと思います。
この記事を読んでくれた方にはこちらの記事もおすすめです。

